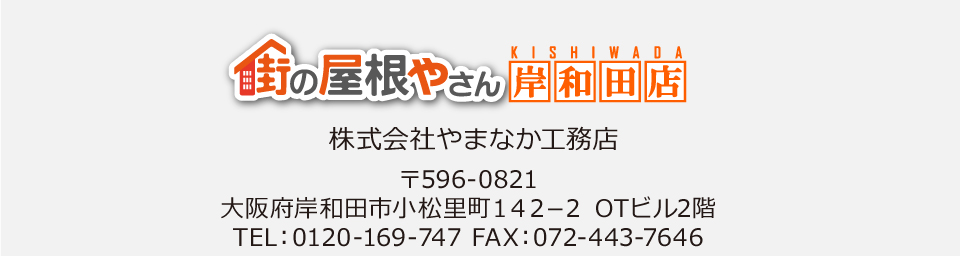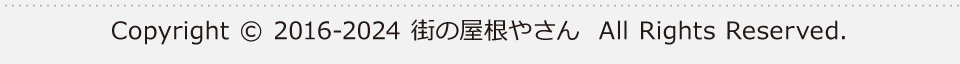2026.02.20
こんにちは。街の屋根やさん岸和田店です。お家の外壁の色褪せ気になりませんか?和泉市にお住まいのN様より「外壁の塗り替え時期が来ているので見に来てほしい」とご相談をいただきました。現場調査を行うと、サイディングのシーリング劣化が見られたため、外壁修繕工事と外壁塗装・外壁リフォームを…
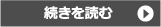






雨漏り☔の原因を特定するため、屋根瓦の状態を確認させていただきました。
すると、瓦が全体的に波打っており、調査の際、瓦の上に足👣を置くと、ズルっとずれてしまうような状態でした。
瓦の下には、瓦を固定するための葺き土という土があるのですが、その葺き土が経年により乾燥していることが、瓦のずれを引き起こしている原因でした。
「葺き土(ふきつち)」とは・・・
瓦屋根を施工する際に、瓦の下に敷いて固定するための土のことです。主に日本瓦などの伝統的な屋根工法で使われます。
粘り気のある土(粘土)を使い、瓦をしっかりと屋根に固定する役割があり、瓦の下に詰めることで、防水性・耐久性・断熱性が高まります。

が見えている.jpg)
紐丸瓦(ひもまるがわら)とは・・・
紐丸瓦は、日本瓦の屋根の棟(屋根の頂上部分や隅の部分など)に使われる瓦の一種です。断面が半円状をしており、棟の लाइनを美しく見せるとともに、棟部分からの雨水の浸入を防ぐ役割があります。棟瓦の一番外側に、紐のように見える形状をしていることから「紐丸瓦」と呼ばれています。
紐丸瓦が浮いてしまった原因として、葺き土の流出・乾燥・地震や強風の影響・経年劣化などが考えられます。



今回、特に下屋の瓦のずれや浮きが顕著でしたので、下屋の屋根材を端から端まで全て撤去し、新たに屋根板金による立平葺きにすることを提案いたしました。
屋根板金による立平葺きとは・・・
金属板を縦方向に葺いていく屋根の工法のひとつで、主にガルバリウム鋼板などの金属を使って仕上げる屋根材・工法の名前です。見た目がスッキリしていて、現代的な住宅や倉庫、店舗などでもよく使われています。
現在の屋根の構造として、大屋根の下に下屋が一部入り込んでいる形になっています。下屋と重なっている大屋根の瓦の下から2列分をめくり、下屋の板金を差し込む形で葺き直します。また、屋根に向かって左側は隅棟も撤去し全て板金で仕上げます。向かって右側は隅棟とそれに続く屋根面の瓦は、新しい瓦を葺く際に、既存の瓦との取り合いをスムーズに行うため、3列分を残して残りの部分は板金に葺き直すことをご提案させていただきました。特に、瓦の種類や形状が異なる場合、既存の瓦を残すことで、雨水の浸入を防ぎ、仕上がりを美しくすることができます。
またなぜ瓦ではなく板金にするのか?
今回、下屋の屋根材を瓦から板金にする主な理由は
軽量性(けいりょうせい): 板金は瓦に比べて非常に軽いため、建物への負担を軽減できます。
防水性(ぼうすいせい): 板金は継ぎ目をしっかりと処理することで、高い防水性を発揮します。今回のK様邸のように、雨漏りが深刻な状況であった場合、より確実な防水対策として板金が選ばれることがあります。
施工性(せこうせい): 板金は瓦に比べて施工が比較的 早くかつ容易です。工期の短縮やコスト削減にもつながります。

街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん岸和田店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.